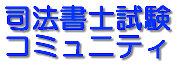解答
不正解
正解は、肢 3
正答率 : 12301/28225 ( 43.6% )
| 肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
| 1 | ア・イ | 5050 |  17.9% 17.9% |
|---|
| 2 | ア・オ | 3967 |  14.1% 14.1% |
|---|
| 3 | イ・ウ | 12301 |  43.6% 43.6% |
|---|
| 4 | ウ・エ | 3620 |  12.8% 12.8% |
|---|
| 5 | エ・オ | 3268 |  11.6% 11.6% |
|---|
解説文を読む | 問題リストへもどる
民法:無権代理:昭57-5,昭58-1,昭62-2,平3-1,平6-4,平7-4,平8-3,平9-3,平13-3,平14-2,平15-6
解説
- ア
- 正しい
民法115条。代理権を有しない者がした契約は,本人が追認をしない間は,相手方が取り消すことができる(民法115条本文)。ただし,契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは,この限りでない(民法115条ただし書)。これは,無権代理人と契約を締結した相手方は,本人の追認があれば本人に責任を追及することができるが,追認するかどうかは本人の自由であるため,その間,不安定な地位におかれる相手方を保護する趣旨である。本記述においては,無権代理行為の相手方Bは,契約当時においてAが代理権を有していないことを知らなかったのであるから,売買契約を取り消すことができる。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
無権代理契約が本人の追認拒絶により無効と確定した場合,無権代理人は,相手方の選択に従い,同人に対して,契約の履行又は損害賠償の責任を負う(民法117条1項)。もっとも,相手方が,無権代理人に代理権がないことを知っていた場合,又は,過失によって知らなかった場合は,かかる責任を追及することはできない(民法117条2項)。これは,無権代理の効果が本人に帰属しない場合に,表見代理とならなくても,代理行為の相手方をできるかぎり保護して取引の安全を図り,かつ代理制度の信用を維持しようとする趣旨である。本記述においては,相手方Bは無権代理人Aが代理権を有しないことを知らなかったものの,知らないことにつき過失があったのであるから,無権代理人の責任(民法117条1項)を追及することはできない(民法117条2項)。従って,BはAが代理権を有していないことにつき過失があるときでも無権代理人の責任を追及することができるとしている点で,本記述は誤っている。
- ウ
- 誤 り
無権代理人が本人から無権代理行為の目的物を譲り受けた場合の法律関係について,判例は,無権代理人は,民法117条の定めるところにより,相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責に任ずべく,相手方が履行を選択し無権代理人が前記不動産の所有権を取得するにいたった場合においては,前記売買契約が無権代理人自身と,相手方との間に成立したと同様の効果を生ずると解するのが相当であると判示した(最判昭41.4.26)。本記述においては,無権代理人Aが本人Cから無権代理行為の目的物たる甲土地を譲り受けており,相手方Bは履行を請求しているから,甲土地の所有権は相手方Bに帰属することになる。そして,所有権移転の時期について,「真の所有者より他人物売買の買主への本件物件の所有権及び占有移転の時期,方法につき特段の約定ないし意思表示がない限り他人物売買の売主が真実の所有者より本件物件の所有権を取得すると同時に他人物売買の買主が他人物売買の売主より本件物件の所有権を取得」する(最判昭40.11.19),とした判例の趣旨に照らし,無権代理人が特定物の所有権を譲渡により取得したときに無権代理人から相手方に物権変動が生じると考えられている。従って,甲土地の所有権はAB間の売買契約時に遡ってBに帰属することになるとしている点で,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
最判昭37.4.20。無権代理人が死亡して本人が無権代理人を相続した場合において,判例は,無権代理行為は当然に有効となるものではなく,本人がその資格において追認を拒絶しても信義則に反しないとする(最判昭37.4.20)。よって,本記述のように本人Cが無権代理人Aを単独相続したときには,Cは本人の資格において追認を拒絶することができる。従って,本記述は正しい。
- オ
- 正しい
最判昭40.6.18。本人が死亡し,無権代理人が相続した場合において,判例は,無権代理行為は当然に有効になり,本人の資格で追認を拒絶することはできないとする(最判昭40.6.18)。よって,本記述のように,無権代理人Aが本人Cを単独相続したときには,無権代理行為は当然に有効になる。そして,物の所有権は意思表示のみによって移転するから(民法176条),Bは当然に甲土地の所有権を取得することになる。従って,本記述は正しい。
以上により,誤っている記述はイとウであり,従って,正解は肢3となる。
この問題・解答・解説の著作権は、辰已法律研究所様にあります。司法書士試験コミュニティは、辰已法律研究所様と業務提携関係を締結して、掲載を許可されております。コンテンツの全部または一部を無断で転載・複製(コピー)することは禁じられています。
スポンサード リンク
|