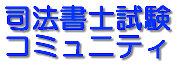解答
不正解
正解は、肢 2
正答率 : 10855/22258 ( 48.8% )
| 肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
| 1 | ア・イ | 4804 |  21.6% 21.6% |
|---|
| 2 | ア・エ | 10855 |  48.8% 48.8% |
|---|
| 3 | イ・ウ | 2107 |  9.5% 9.5% |
|---|
| 4 | ウ・オ | 1899 |  8.5% 8.5% |
|---|
| 5 | エ・オ | 2572 |  11.6% 11.6% |
|---|
解説文を読む | 問題リストへもどる
民法:取消しの当事者:平5-8,平12-1
解説
- ア
- 正しい
民法120条1項。民法120条1項は,「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者に限り,取り消すことができる」と規定し,取消権者に制限行為能力者を挙げている。そのため,未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないでした売買契約を単独で取り消すことができる。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができる(民法120条2項)。保証人は,この取消権者に含まれておらず,保証人が主債務者の取消権を行使できるかにつき,判例も,これを否定している(大判昭20.5.21)。そのため,CがBの詐欺によってBに対して債務を負うに至った場合,Cの債務を保証したAは,Cがした契約を取り消すことができない。従って,本記述は誤っている。
- ウ
- 誤 り
民法120条1項は,「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者に限り,取り消すことができる」としている。そして,保佐人には同意権があるため(民法13条1項柱書),保佐人は被保佐人の行為を取り消すことができる。よって,保佐人Aは,被保佐人Bのした契約を取り消すことができる。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
BがCの詐欺によってBの不動産をCに売り渡した場合,BはCに対して取消権を有する(民法96条1項)。そして,このような取消権等の形成権が債権者代位権(民法423条)の対象になり得ることは一般的に承認されている。そのため,BがCの詐欺によってBの唯一の財産である不動産をCに売り渡した場合,Bは無資力であることから,Bの債権者Aは,Bに代位してBC間の契約を取り消すことができる。従って,本記述は正しい。
- オ
- 誤 り
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができる(民法120条2項)。よって,詐欺によって不動産を売り渡した者は,その意思表示を取り消すことができる。この場合,取り消すことができる行為の相手方が確定しているときは,その取消しは,相手方に対する意思表示によってする(民法123条)。よって,本記述の場合,Aは,意思表示の相手方であるBに対して,取消しの意思表示をする必要がある。従って,本記述は誤っている。なお,本問の事例では,Bが詐欺の事実を知っていたときに限り,Bに対して取消しの意思表示をすることができる(民法96条2項)。
以上により,正しい記述はアとエであり,従って,正解は肢2となる。
この問題・解答・解説の著作権は、辰已法律研究所様にあります。司法書士試験コミュニティは、辰已法律研究所様と業務提携関係を締結して、掲載を許可されております。コンテンツの全部または一部を無断で転載・複製(コピー)することは禁じられています。
スポンサード リンク
|
|