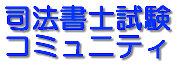解答
正解
正答率 : 3577/12835 ( 27.9% )
| 肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
| 1 | ア・イ | 2845 |  22.2% 22.2% |
|---|
| 2 | ア・エ | 1890 |  14.7% 14.7% |
|---|
| 3 | イ・オ | 2760 |  21.5% 21.5% |
|---|
| 4 | ウ・エ | 1759 |  13.7% 13.7% |
|---|
| 5 | ウ・オ | 3577 |  27.9% 27.9% |
|---|
解説文を読む | 問題リストへもどる
不動産登記法:登録免許税:昭57-24,昭58-27,昭59-29,昭60-16,昭61-29,平元-25,平2-30,平3-28,平4-30,平5-19,平6-20,平7-13,平9-18,平1
解説
- ア
- 正しい
登録免許税法別表1.1(5)。不動産を目的とする担保権の実行は,担保不動産競売,若しくは,担保不動産収益執行の方法により行われる(民執法180条)。そして,担保不動産収益執行の申立てがなされた場合に,その開始決定がなされたときは,裁判所書記官は,直ちに,その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない(民執法188条,111条,48条)。この登記が嘱託されるときに納付される登録免許税の額は,債権金額に1000分の4の税率を乗じた額となる(登録免許税法別表1.1(5))。従って,本記述は正しい。
- イ
- 正しい
登録免許税法22条。書面により登記を申請する場合において,登記を受ける者は,原則として,当該登記における登録免許税の額を国に納付し,当該納付に係る領収証書を当該登記の申請書にはり付けて提出する(登免法21条,現金納付)。しかし,当該登記における登録免許税の額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には,当該登録免許税の額に相当する印紙を当該登記の申請書にはり付けて提出することにより,国に納付することができる(登免法22条,印紙納付)。従って,本記述は正しい。
- ウ
- 誤 り
登記を受けた者は,当該登記の申請書に記載した登録免許税の税額の計算に誤りがあったことにより,登録免許税の過誤納があるときは,当該登記等を受けた日から1年を経過する日までに,政令で定めるところにより,その旨を登記機関に申し出て,納税地の所轄税務署長に通知をすべき旨の請求をすることができる(登免法31条2項,1項)。よって,納税地の所轄税務署長に対し,直接,登録免許税の還付請求をすることができるわけではない。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
登記の申請を取り下げる際に再使用証明を受けた登録免許税の領収証書又は印紙は,再使用証明を受けた登記所においてのみ使用でき,他の登記所において使用することはできない(登免法31条3項,登研321P.71)。従って,本記述は正しい。
- オ
- 誤 り
不動産登記の申請を取り下げる際に再使用証明を受けた登録免許税の領収証書又は印紙は,商業登記の申請にも使用することができる(登研393P.87)。従って,本記述は誤っている。
以上により,誤っている記述はウとオであり,従って,正解は肢5となる。
この問題・解答・解説の著作権は、辰已法律研究所様にあります。司法書士試験コミュニティは、辰已法律研究所様と業務提携関係を締結して、掲載を許可されております。コンテンツの全部または一部を無断で転載・複製(コピー)することは禁じられています。
スポンサード リンク
|